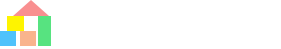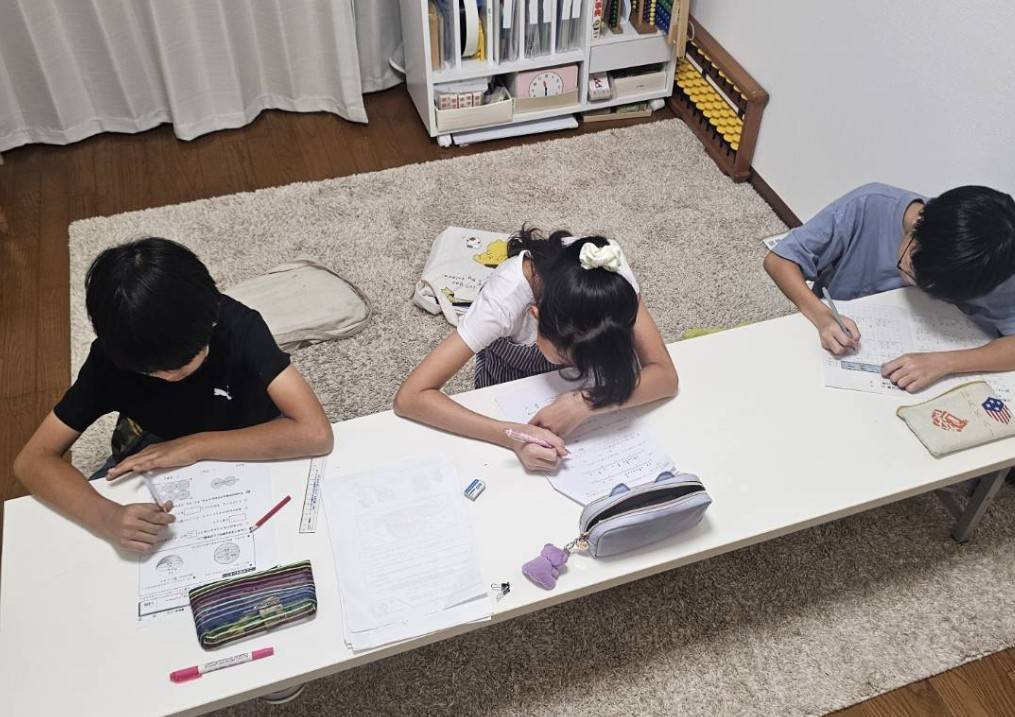「プリントやってね」と声をかけても、
ダラダラしたり、逃げたり、机に向かってくれなかったり…。
「どうしてやってくれないの?」
「このままで勉強についていけるのかな…」
と、不安になってしまうママ・パパも多いと思います。
でも、「やらない=やる気がない・頭が悪くなる」ではありません。
多くの場合、
・タイミング
・声のかけ方
・プリントとの付き合い方
を少し変えるだけで、子どもはスッと動きやすくなります。
ここでは、「なかなかプリントをしてくれない」ときに見直したいポイントを3つお伝えします。
ポイント①「やらない」の裏にある気持ちを考えてみる
まずは、「なぜプリントをしないのか?」を、
子どもの立場から想像してみることがスタートです。
例えばこんな理由が隠れていることが多いです。
- 幼稚園や学校から帰ってきて、もうクタクタ
- プリントの量が多くて、「終わるイメージ」がわかない
- ちょっと難しくて、「わからない=やりたくない」になっている
- 遊びの途中で声をかけられ、気持ちの切り替えが追いつかない
「なんでやらないの!」と責める前に、
一度立ち止まって、
「今日は疲れてるのかな?」
「このプリント、今のレベルに合っているかな?」
と考えてみると、関わり方のヒントが見えてきます。
ポイント②やるタイミングと量を“小さく決める”
プリント習慣で大切なのは、
「一気にたくさん」より「少しを続ける」ことです。
タイミングの工夫
- 帰宅直後のぐったりタイムは避けて、
少しおやつを食べて落ち着いてからにする - 「○時になったらプリント、終わったら自由時間ね」と
事前に流れを決めておく
量の工夫
- 「1枚やろう」ではなく「この列だけ」「3問だけ」から始める
- 「全部終わらなくてもOK、ここまでできたら今日の合格!」と
先にゴールを小さく決める
「これならできそう」と子どもが感じられる量とタイミングにすると、
自分からスッと動ける確率がぐっと上がります。
ポイント③“プリント=作業”ではなく“対話の時間”にする
プリントが「ただの作業」になると、
子どもはつまらなくなってしまいます。
少しだけ、親子の対話を足してあげると、
プリントの時間が「勉強」から「楽しい発見の時間」に変わります。
例えば…
- 解く前に 「この問題、どうやって考えたらよさそう?」
- 解いたあとに 「どうしてそう思ったの?考え方教えて」
- 間違えたときも 「ここまでの考え方はよかったね。じゃあ、どこからずれたかな?」
と、“できた・できない”だけでなく、
考え方そのものをほめる・聞くことがポイントです。
こうしたやりとりを重ねることで、
プリントは「言われたからやるもの」から
**「自分の頭で考える練習」**に変わっていきます。
それが、後々の思考力・算数力・読解力につながっていきます。
最後に
「なかなかプリントをしてくれない」というお悩みは、
どのご家庭でも一度は通る道です。
大切なのは、
- やらない理由を子どもの目線で考えてみる
- タイミングと量を小さく整える
- プリントを“作業”ではなく“対話と発見の時間”にする
この3つを、完璧でなくていいので、
できる範囲で少しずつ取り入れてみることです。
幼児教室しばたでは、
「プリントをこなすこと」よりも、
“考えるって楽しい”“わかるって気持ちいい”
という気持ちを育てることを大切にしています。
おうちのプリント時間も、
親子で一緒に“考える力”を育てていける時間になりますように。